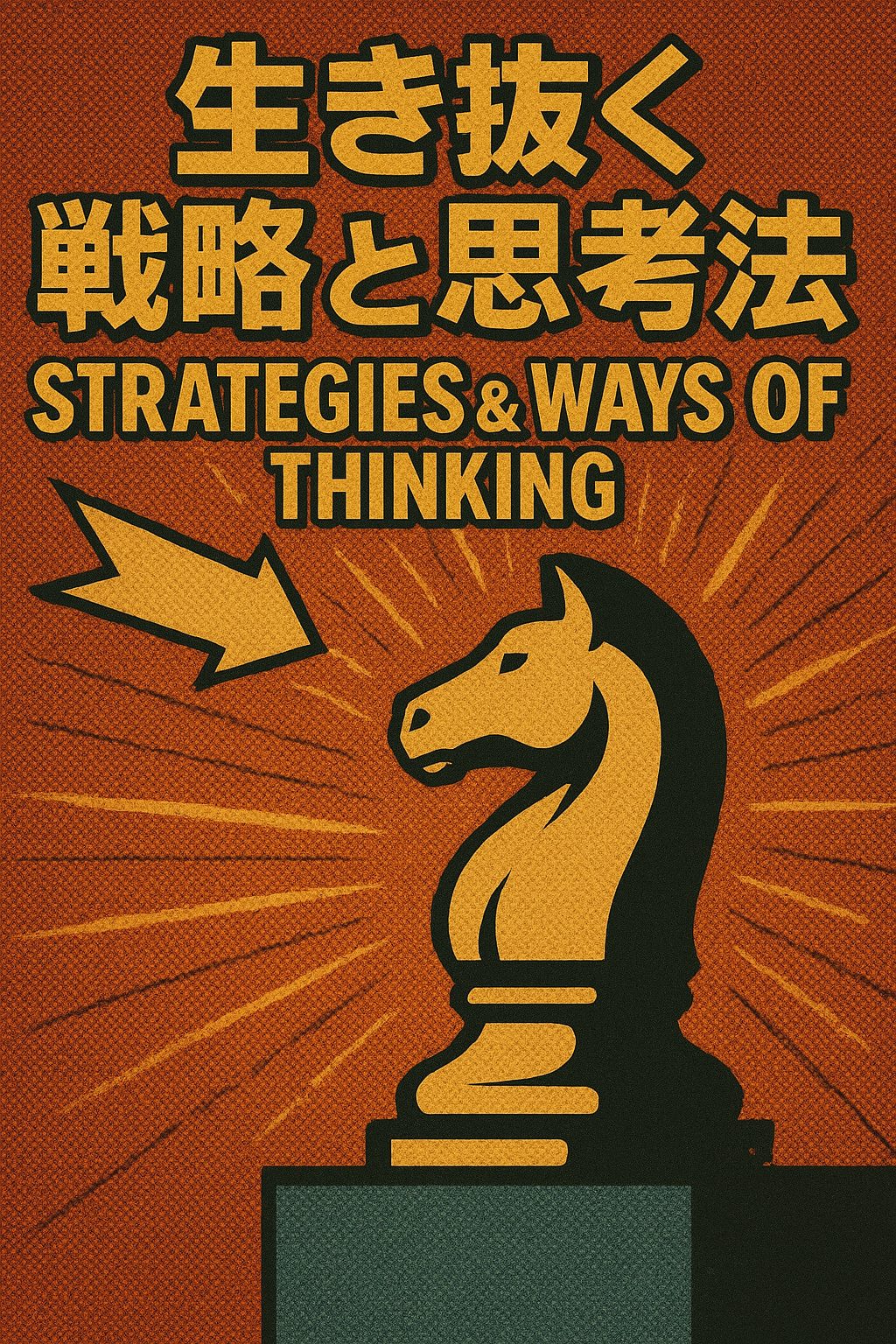キャリアづくりの教科書を要約|AI時代を生き抜く戦略と思考法
スポンサードサーチ
キャリアづくりの教科書 要約|AI時代を生き抜く実践知
「このままの働き方でいいのだろうか」「AIに仕事を奪われないためには?」——そう感じたことがある人にこそ読んでほしい一冊が、長谷川高氏の『キャリアづくりの教科書』です。
本書は、変化の激しい時代に“キャリアを設計する力”を育むための実践ガイド。
単なる転職ノウハウではなく、「自分の市場価値を構築する戦略書」として高く評価されています。
キャリアづくりの教科書 要約:3つの柱

本書が提唱するキャリア設計の3本柱は次の通りです。
- 自分の強みを再定義する「棚卸し」
- 職務経歴ではなく「価値提供のストーリー」を描く。
- 他者評価を活用し、自分では気づけない強みを見出す。
- AI時代を見据えたスキル構築
- AIに代替されない領域=創造性・対人スキル・構想力。
- ChatGPTや自動化ツールを“道具”として使いこなす発想が重要。
- 長期視点でのキャリア資産形成
- 転職は目的ではなく、「キャリア資産の交換」の一形態。
- スキル・人的ネットワーク・発信力の3要素で市場価値を高める。
💡 ポイント:「何をやるか」ではなく「どう成長するか」を設計することが、キャリアの持続性を決める。
スポンサードサーチ
AI時代に求められる“キャリア戦略思考”

AIが進化する中で、「努力すれば報われる」時代は終わりました。
今必要なのは、努力の方向を設計する力です。
『キャリアづくりの教科書』では、AIによって変化する職業構造を冷静に分析し、「代替される仕事」「代替されにくい仕事」を見極める思考法が紹介されています。
特に注目すべきは以下の3つ。
- 情報編集力:AIが生成した情報を取捨選択し、価値に変える。
- 対人影響力:他者の意思決定を促す力(共感・プレゼン・交渉)。
- 戦略的自己発信:SNSやブログで自分の思考・実績を“見える化”する。
アハ体験:「キャリアは“仕事の集積”ではなく、“意思の軌跡”だ」
読了後、多くの人がハッとするのがこの気づきです。
キャリアとは転職回数や肩書きの積み上げではなく、自分がどんな意思で選択してきたかの軌跡。
AIや組織が変わっても、意思だけは自分の手に残ります。
つまり、「キャリアをつくる」とは、他者に任せるものではなく、自分の価値観を社会に翻訳する行為なのです。
この視点を得た瞬間、仕事の不安が「自己設計のチャンス」に変わります。
スポンサードサーチ
よくある質問(FAQ)
Q1. AI時代にキャリアの安定はあり得ますか?
A. 絶対的な安定は消えましたが、「学び続ける力」が最大の安定になります。知識よりも「学習習慣」を仕組み化しましょう。
Q2. どんなスキルを優先的に学ぶべき?
A. ロジカル思考・コミュニケーション・デザイン的思考。この3つはどの業界でもAIの補助を超える“人間の領域”です。
Q3. キャリアの方向性がわからないときは?
A. 自分の「モヤモヤ」を言語化することから始めましょう。モヤモヤの中にこそ、次のキャリアの“種”が眠っています。
まとめ:キャリアづくりは「意図的な試行」の連続
『キャリアづくりの教科書』の本質は、「人生100年時代に、自分をどう再設計するか」。
重要なのは「完璧な計画」ではなく、意図を持った試行錯誤を続ける姿勢です。
AIが仕事を変える今こそ、キャリアの舵を自分の手に取りましょう。
📘 Amazonでチェック
関連記事